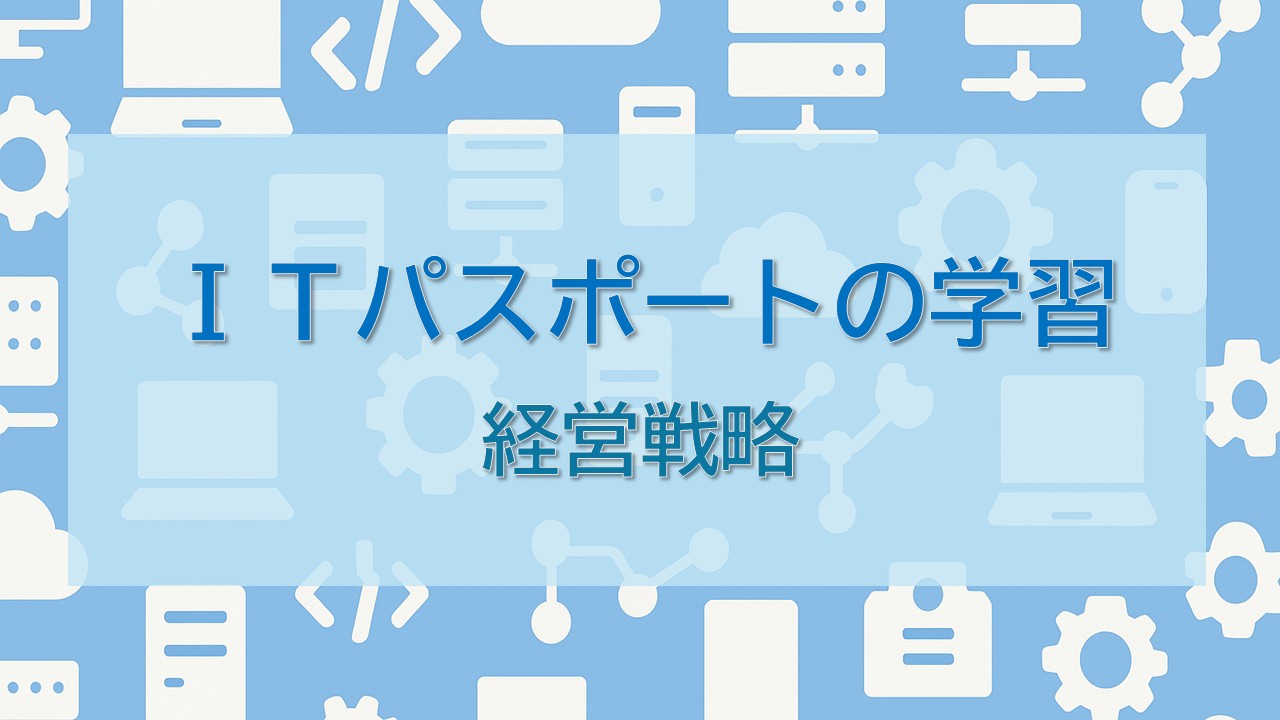CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)
顧客との関係を継続的に築き、満足度やロイヤルティを高める仕組み。
顧客の情報を蓄積・分析し、最適な対応や提案を行う。
売上向上やリピート率向上に大きく貢献する。
例:過去の購入履歴に応じて、個別にクーポンを送る。
バリューチェーンマネジメント
製品やサービスが生まれて顧客に届くまでの価値の流れを管理する方法。
「購買→製造→販売→サービス」などの各工程で付加価値を最大化する。
全体最適を図る視点が重要となる。
例:仕入れから販売までの各部門が連携し、無駄なく効率的に価値を届ける。
SECIモデル
知識を創造・共有・活用する4つのプロセスから成るモデル。
暗黙知と形式知の変換を通じて、組織全体の知識を進化させる。
日本発の知識創造理論として世界的にも有名。
例:ベテラン社員の経験(暗黙知)をマニュアル化(形式知)し、全社で共有する。
SECIモデル(共同化)
経験や感覚といった暗黙知を、他者と共有するプロセス。
言葉や文章ではなく、共に体験することで知識を伝える。
主にOJTや対話、模倣、共同作業などによって行われる。
例:先輩社員と一緒に現場を回って、仕事のコツを体感で覚える。
SECIモデル(表出化)
共有された暗黙知を、言葉や図などの形式知に変換するプロセス。
暗黙知を説明可能な形にすることで、他人が理解しやすくなる。
マニュアル化や議論を通じた明文化が中心となる。
例:現場で得たコツを図解付きの手順書にまとめる。
SECIモデル(連結化)
複数の形式知を整理・統合し、より高度な知識体系を作るプロセス。
個人が持つ知識や情報を組み合わせて、組織的に活用できる知識にする。
データベース化や報告書の取りまとめなども該当する。
例:各部署のマニュアルを集めて標準作業フローとしてまとめる。
SECIモデル(内面化)
形式知を自らの経験に照らして再び暗黙知として吸収するプロセス。
教育や実践を通じて、知識が「できること」として身につく段階。
学習によって個人のスキルや判断力が向上する。
例:マニュアルを読み込み、実際に手を動かして作業を習得する。
SCM(Supply Chain Management:供給連鎖管理)
原材料の調達から製品の納品まで、全体の流れを統合的に管理する考え方。
企業間の連携によってコスト削減や納期短縮を目指す。
グローバルな調達や物流にも活用される。
例:製造会社が部品メーカーや運送会社と連携し、生産・配送を最適化する。
TQC(Total Quality Control:全社的品質管理)
品質管理を経営の中心に据え、全社員で取り組む考え方。
製品の完成後だけでなく、企画・設計・製造などすべての工程で品質を向上させる。
顧客満足と信頼を確保するための土台となる。
例:社員全員が品質目標を共有し、日々の改善活動を行う。
TQM(Total Quality Management:総合的品質管理)
TQCを発展させた考え方で、経営全体に品質重視の文化を根づかせる取り組み。
顧客志向、プロセス重視、継続的改善(カイゼン)が基本。
品質を企業文化として定着させることが目的。
例:品質に関する研修を全社員に定期的に実施し、改善提案制度を運用する。
ERP(Enterprise Resource Planning:企業資源計画)パッケージ
財務・人事・生産・在庫など企業の基幹業務を一元管理するソフトウェア。
部門ごとの情報をリアルタイムで共有できるようになる。
業務効率化や経営判断の迅速化に役立つ。
例:受注情報が自動で在庫や会計に連携されるERPシステムを導入する。
シックスシグマ
製品や業務のばらつきを統計的に分析し、不良率を限りなくゼロに近づける品質管理手法。
DMAIC(定義・測定・分析・改善・管理)というプロセスで進められる。
主に製造業で使われるが、サービス業にも応用可能。
例:不良品率を100万個に3.4個以下に抑えることを目標に改善活動を行う。
ナレッジマネジメント
組織内にある知識やノウハウを共有・活用して、組織の競争力を高める活動。
暗黙知を形式知に変換し、ITツールなどを使って全社に広める。
個人の経験が組織の資産として蓄積されていく。
例:社内WikiやFAQデータベースを整備して、新人教育や業務効率化に活かす。
TOC(Theory Of Constraints:制約理論)
業務プロセスの中で最も大きな制約(ボトルネック)を特定し、全体最適を図る理論。
制約が改善されると、全体の生産性が大きく向上する。
一部だけを最適化しても全体の効率は上がらないという考え方に基づく。
例:製造ラインで最も時間がかかる工程に人員を集中して処理速度を改善する。