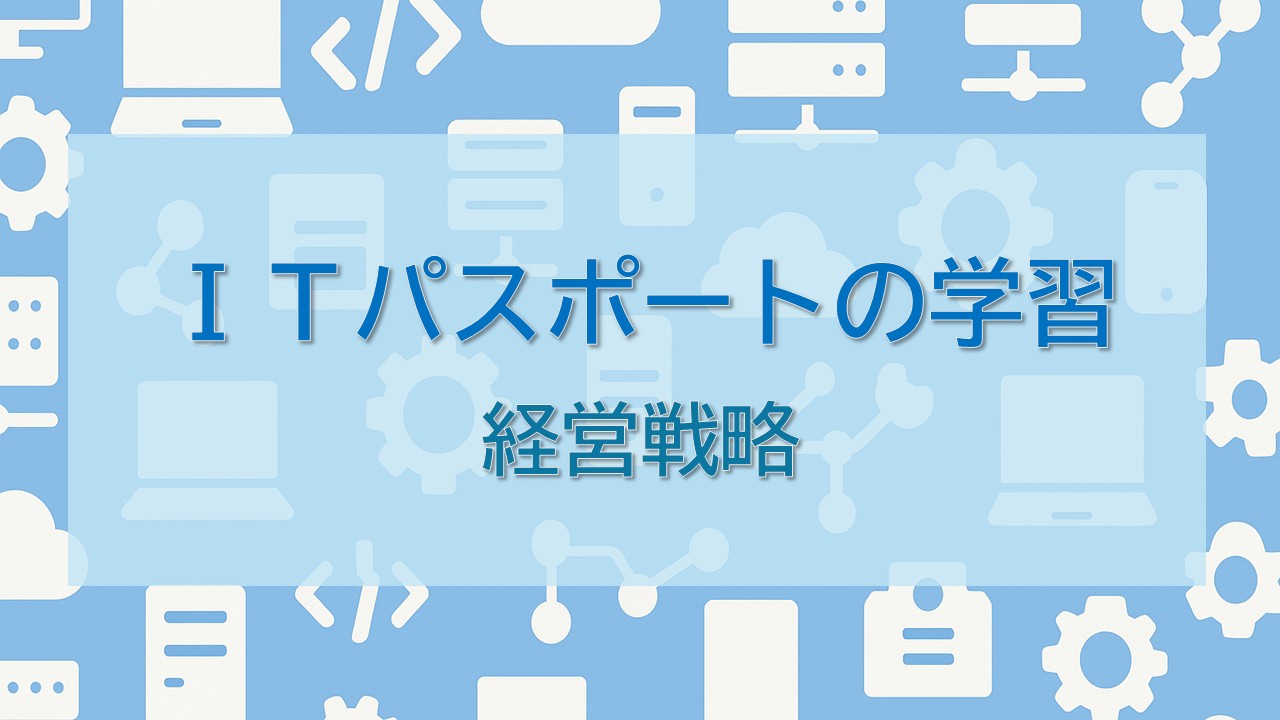フレームワーク
考えを整理するための「枠組み」や「型」のこと。
複雑な問題を分かりやすくし、効率的に分析・解決できる。
経営やマーケティング、論理的思考などでよく使われる。
例:3C分析やSWOT分析、PDCAサイクルなどの思考の道具。
SWOT分析
企業の強み・弱み・機会・脅威を整理する分析手法。
内部環境(Strength, Weakness)と外部環境(Opportunity, Threat)に分けて戦略を考える。
状況把握や戦略立案の基礎として使われる。
例:強み=技術力、脅威=新興企業の参入。
PPM(Product Portfolio Management)
製品や事業を市場成長率と市場シェアで分類する分析手法。
「花形」「問題児」「金のなる木」「負け犬」に分類して戦略を立てる。
資源配分や撤退判断に活用される。
例:成長中で高シェアの製品は「花形」となる。
VRIO分析
企業の競争優位性を4つの観点から評価するフレームワーク。
Value(価値)、Rarity(希少性)、Imitability(模倣困難性)、Organization(組織体制)を確認する。
持続的な優位性があるかを判断する基準になる。
例:独自の技術があり模倣困難であれば、強い競争力を持つとされる。
外部環境
企業の外側にある影響要因。
市場動向、競合、法律、社会情勢などが含まれる。
企業にとって機会にも脅威にもなり得る。
例:新技術の登場、法改正による新たな規制。
内部環境
企業の内部にある経営資源や体制。
人材、技術、ブランド、財務体質などが含まれる。
自社の強みと弱みを把握する材料になる。
例:研究開発力が強い、資金力が弱い。
3C分析
Customer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点から市場を分析する手法。
市場理解と戦略立案の出発点として使われる。
バランスよく情報を整理できるのが特徴。
例:顧客ニーズに合った商品を、競合より魅力的に提供する。
競争優位
他社よりも有利な立場で市場に立てる状態。
コスト、品質、ブランド、技術などで差別化できることが重要。
持続可能な競争優位が企業成長の鍵となる。
例:高い技術力で他社にまねできない製品を提供する。
イノベーション
新しい価値を生み出す革新や技術のこと。
製品、サービス、ビジネスモデルなどさまざまな分野に起こり得る。
既存の常識を破ることで競争力を高める。
例:スマートフォンの登場による通信業界の変革。
コアコンピタンス
企業の中核となる強みや独自の能力。
他社にまねできない価値創造の源泉。
企業戦略の土台となる重要な要素。
例:独自の製造技術や設計思想など。
ニッチ戦略
市場の中でも特定の狭い分野に集中する戦略。
大手が手を出しにくい分野で強みを発揮する。
小規模企業でも高いシェアを取れる可能性がある。
例:高齢者向けの専用パソコンを開発して販売する。
同質化戦略
他社と差をつけず、類似した製品やサービスで市場に参入する戦略。
価格競争になりやすく、コスト管理が重要。
市場全体の成熟期に使われることが多い。
例:すでに普及した製品と同じ機能を持った製品を低価格で販売する。
ブルーオーシャン戦略
競争相手がいない新たな市場を創り出す戦略。
差別化と低コストを両立して新規需要を開拓する。
レッドオーシャン(競争の激しい市場)からの脱却を目指す。
例:これまでになかった新ジャンルの商品を発売して新市場を形成する。
エコシステム
複数の企業が連携して作る共存共栄のビジネス環境。
製品やサービスを補完し合いながら価値を高める。
全体としての競争力が強まる。
例:スマートフォンとアプリ開発会社、アクセサリーメーカーの連携。
アライアンス
企業同士が提携して協力する戦略。
資本提携、業務提携などの形で行われる。
コスト削減や新市場進出などを目的とする。
例:他社と共同で新製品を開発する業務提携。
アウトソーシング
業務の一部を外部の専門業者に委託すること。
コスト削減や業務の効率化が目的。
自社の中核業務に集中できるメリットがある。
例:給与計算やコールセンター業務を外部企業に任せる。
M&A(Mergers and Acquisitions)
企業の合併や買収のこと。
他社を取り込むことで規模拡大や新分野参入を目指す。
統合後のシナジー(相乗効果)を期待する。
例:IT企業がベンチャー企業を買収して技術力を獲得する。
OEM(Original Equipment Manufacturer)
他社ブランドの製品を製造する仕組み。
製造は自社で行い、販売は他社ブランドで行われる。
メーカーは製造に集中し、ブランド側は販売に注力できる。
例:自社が作ったパソコンを別会社のロゴで販売する。
ファブレス
自社で工場を持たずに製品を企画・設計し、製造は外部に委託するビジネスモデル。
設備投資を抑えつつ、開発やマーケティングに注力できる。
リスク回避やスピード向上につながる。
例:半導体メーカーが生産を全て外注に任せる。
フランチャイズチェーン
本部と加盟店が契約を結び、同じブランドや仕組みで営業する方式。
加盟店は本部の支援を受けて経営する。
迅速な店舗展開やブランドの統一が可能になる。
例:飲食チェーン店が全国展開する際の仕組み。
MBO(Management Buyout)
企業の経営陣が自社の株式を買い取り、会社の経営権を取得すること。
経営の自由度を高め、長期的な視点での運営が可能になる。
非上場化を目指すこともある。
例:上場企業の社長が投資家と連携して株式を買い取る。
TOB(Take Over Bid)
株式を公開で買い付けて企業を買収する方法。
既存株主に対して一定価格で株を買い取ることを公表して行う。
敵対的TOBと友好的TOBがある。
例:新聞で「A社がB社に対してTOBを開始」と発表される。
規模の経済
生産規模が大きくなることで1単位あたりのコストが下がる現象。
大量生産により原材料や設備のコストが抑えられる。
価格競争に強くなる。
例:製品をまとめて大量に仕入れることで1個あたりのコストが下がる。
経験曲線
経験を積むほど効率が上がり、生産コストが下がることを示す法則。
時間とともに作業が熟練されていく現象。
量をこなすことで競争優位が得られる。
例:同じ製品を作り続けることで作業時間が短縮される。
垂直統合
製品の製造から販売までを自社で一貫して行う体制。
中間業者を省くことでコスト削減や品質管理が可能になる。
製造業や流通業でよく見られる。
例:農場から加工・販売までをすべて自社で行う食品企業。
コモディティ化
製品やサービスの差別化が失われ、価格競争になる状態。
特徴がなくなり、どの企業の製品でも同じと見なされる。
利益率が低下するリスクがある。
例:家電製品がどのメーカーも似た機能になってしまう。
ベンチマーキング
他社の優れた事例を調査・分析して、自社の改善に活かす手法。
競合や業界トップ企業の行動を参考にする。
継続的改善(カイゼン)の出発点になる。
例:配送時間を短縮するために他社の物流手法を調査する。
ロジスティクス
原材料の調達から製品の配送までを含む物流全体の管理。
在庫管理、輸送、保管などを効率化する。
企業のコスト削減とサービス向上に直結する。
例:注文から24時間以内に届けるための配送体制を構築する。
カニバリゼーション
自社の新商品が、既存商品の売上を奪ってしまう現象。
「共食い」とも呼ばれ、全体の売上が伸び悩む要因になる。
商品ラインの設計や販売戦略の調整が必要。
例:新しいモデルの発売で旧モデルの売上が急減する。
ESG投資
環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に配慮した企業に投資する手法。
短期的な利益だけでなく、持続可能性や社会的責任を重視する。
長期的な成長や安定性を期待する投資家が選択する。
例:再生可能エネルギーに取り組む企業への株式投資。