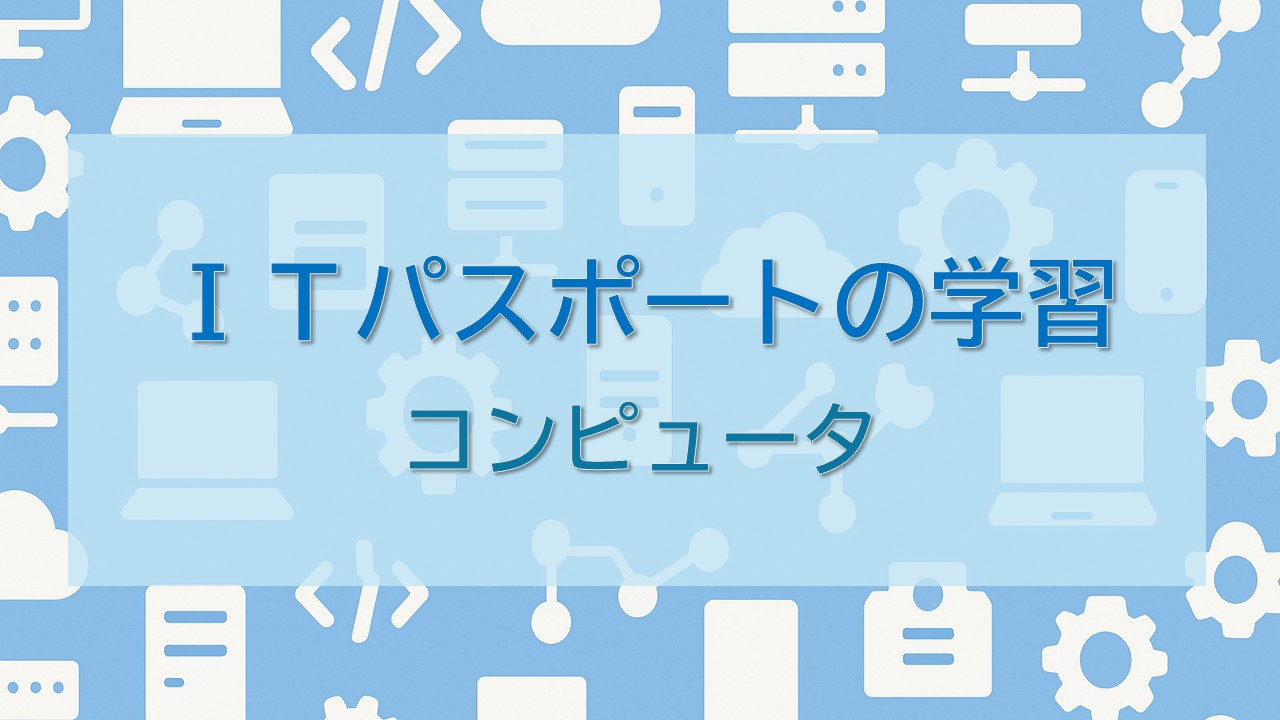メモリ
データやプログラムを一時的に記憶する装置。
処理中に使用する情報を一時的に保持する役割を持つ。
主記憶装置として、CPUとデータのやりとりを行う。
例:作業中のファイルが保存される場所がメモリ。
RAM
ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory)の略で、読み書き可能な記憶装置。
電源を切ると内容が消える揮発性メモリに分類される。
主記憶装置として、作業中のデータを保持する。
例:画像編集中のデータが一時的にRAMに格納されている。
ROM
リードオンリーメモリ(Read Only Memory)の略で、読み出し専用の記憶装置。
電源を切っても内容が消えない不揮発性メモリ。
システム起動に必要な基本プログラム(BIOSなど)が記録されている。
例:パソコンの起動時に使用される初期設定情報がROMに記録されている。
揮発性メモリ
電源を切ると記憶内容が消えるタイプのメモリ。
高速に読み書きできるが、長期保存には向かない。
主にRAMが該当する。
例:作業中に保存していないデータが、停電で消えるのは揮発性メモリの特性。
不揮発性メモリ(フラッシュメモリ)
電源を切っても記憶内容が保持されるメモリ。
データの保存や持ち運びに適している。
USBメモリやSSDなどに使用される。
例:デジカメの写真が入っているSDカードはフラッシュメモリ。
DDR3 SDRAM
第3世代のDDR(Double Data Rate)型同期DRAM。
以前のDDR2よりも高速・低消費電力なメモリ。
多くのパソコンで標準的に使われていた。
例:少し前のノートパソコンではDDR3が主流だった。
DDR4 SDRAM
DDR3の後継として登場した、第4世代の同期DRAM。
動作速度が向上し、省電力性も改善されている。
現在多くのPCやサーバーで使われている標準的なメモリ。
例:2020年代前半のノートパソコンに搭載されることが多い。
DDR5 SDRAM
最新世代のDDR型同期DRAMで、DDR4よりさらに高速化された。
転送速度や容量の向上が図られ、大規模処理に適している。
今後の高性能PCやゲーミングPCなどに広く普及する見込み。
例:AIやゲーム開発向けのハイスペックPCに搭載される。
DIMM(Dual Inline Memory Module)
デスクトップPCで使われる標準的なメモリモジュール。
長方形の基板に複数のメモリチップが搭載されている。
差し込むだけで簡単に増設・交換できる。
例:メモリ増設のためにDIMMスロットに新しいメモリを追加する。
SO-DIMM(Small Outline DIMM)
ノートパソコン向けの小型メモリモジュール。
DIMMと比べてサイズが小さく、省スペース設計になっている。
ノートPCや省スペースデスクトップに使用される。
例:ノートパソコンの裏面を開けるとSO-DIMMが取り付けられている。
HDD(Hard Disk Drive)
ハードディスクドライブの略。
磁気ディスクにデータを記録する補助記憶装置。
大容量で安価だが、衝撃や読み書き速度には弱点がある。
例:1TBのHDDに写真や動画を保存している。
SSD
ソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略。
フラッシュメモリを使った高速な補助記憶装置。
HDDに比べて衝撃に強く、読み書き速度も速い。
例:OSの起動時間がHDDより格段に速いSSDを使う。
CD(CD-ROM,CD-R)
光ディスクの一種で、CD-ROMは読み出し専用、CD-Rは一度だけ書き込み可能。
音楽やソフトウェアの配布に利用されてきた。
現在は使用頻度が減っているが、資料保存などには使われる。
例:CD-Rに卒業アルバムの写真を焼いて配布する。
DVD(DVD-ROM,DVD-RAM,DVD-R)
CDよりも大容量の光ディスク。
DVD-ROMは読み出し専用、DVD-RAMは書き換え可能、DVD-Rは1回書き込み型。
映像メディアやデータバックアップに使われる。
例:映画を保存したDVD-ROMを再生する。
ブルーレイディスク
高解像度映像や大容量データの記録に対応した光ディスク。
DVDよりも大きな容量を持ち、HD映像の保存に最適。
専用の再生機器が必要となる。
例:4K映画をブルーレイディスクに保存して視聴する。
USBメモリ
フラッシュメモリを内蔵した、持ち運び可能な補助記憶装置。
パソコンのUSB端子に直接接続して使える。
小型で手軽に使えるため、データの受け渡しに便利。
例:発表用の資料をUSBメモリに保存して学校に持参する。
SDカード
小型のフラッシュメモリカードで、主にデジタルカメラやスマートフォンに使われる。
microSDカードはさらに小型で、スマホやタブレット向け。
容量や転送速度によって種類が分かれている。
例:デジカメの写真をSDカードに保存してパソコンで取り込む。
キャッシュメモリ
CPUとメモリの間にある、高速な記憶装置。
よく使うデータを一時的に保存して、処理を高速化する。
CPU内部またはその近くに搭載されている。
例:同じデータを繰り返し使うとき、キャッシュからすばやく読み出せる。
主記憶
コンピュータがプログラム実行時に直接利用するメモリ領域。
一般にはRAMを指し、電源が切れると内容は消える。
CPUと直接やりとりするため、処理速度に影響する。
例:作業中の文書ファイルは主記憶に一時保存されている。
補助記憶
データやプログラムを長期間保存するための記憶装置。
HDDやSSD、CD、DVD、USBメモリなどが該当する。
主記憶よりも容量が大きく、保存性に優れる。
例:授業の動画ファイルを補助記憶に保存しておく。