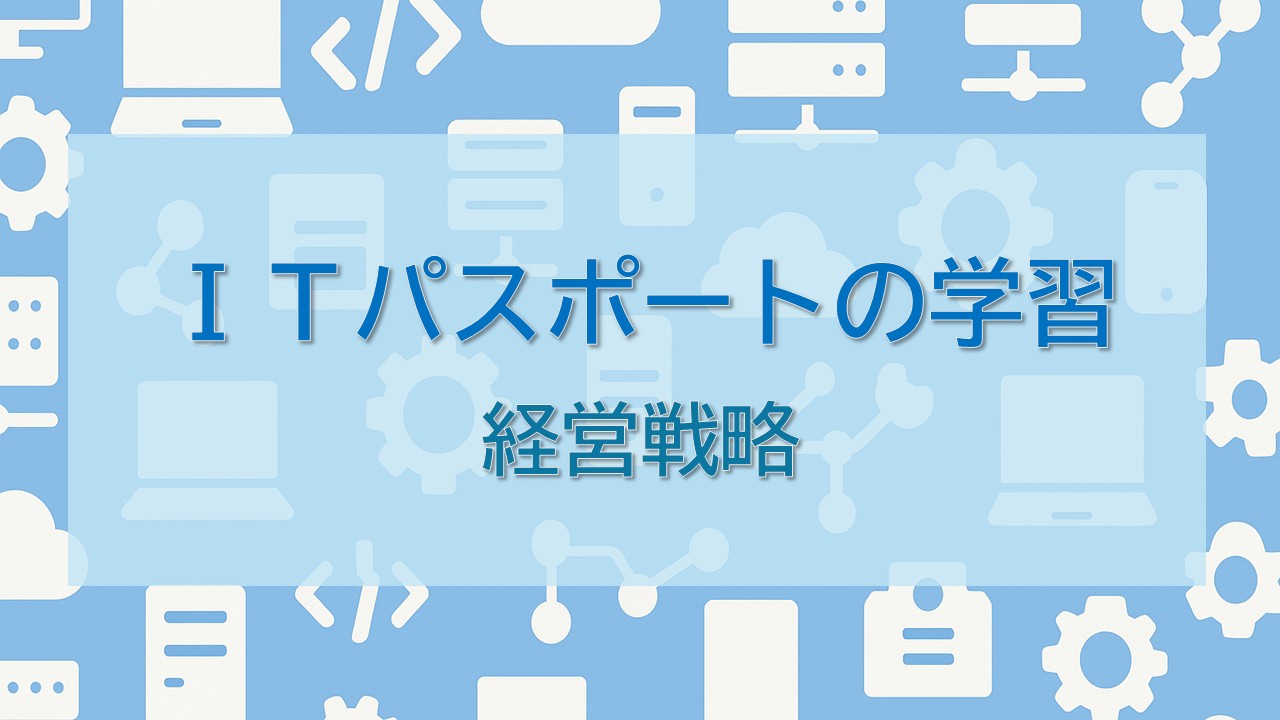市場調査
市場のニーズや動向を調べる活動。
顧客が何を求めているか、競合がどう動いているかを分析する。
新商品開発や販売戦略の基礎となる。
例:アンケートやインタビューで顧客の意見を収集する。
販売・製品・仕入計画
売る商品や仕入れ量、製造タイミングなどを決める。
需要を予測し、無駄なく商品を用意するための基本計画。
季節や流行に合わせて柔軟に調整する必要がある。
例:夏に向けて冷房機器の生産数を増やす。
広告
商品やサービスの情報を多くの人に伝える活動。
テレビCM、Web広告、SNSなどさまざまな手段がある。
認知度を高め、顧客を引きつける第一歩。
例:新商品を紹介する動画をSNSで配信する。
販売促進
買ってもらうために一時的な工夫を加える活動。
クーポン、試供品、ポイント制度などがある。
短期的な売上増加や新規顧客獲得が目的。
例:「今だけ20%オフ」などのキャンペーンを行う。
顧客満足
商品やサービスを利用したときの満足の程度。
満足度が高いとリピートや紹介につながる。
企業の信頼やブランド向上にも関係する。
例:購入後の丁寧なサポートで信頼感が高まった。
UI(User Interface)
ユーザーとシステムをつなぐ「見た目」や「操作部分」のこと。
ボタンの配置、文字の大きさ、色、画面レイアウトなどが含まれる。
使いやすいUIは、ユーザーのストレスを減らし、満足度を高める。
例:アプリのボタンが大きく押しやすく、誰でも直感的に使える画面設計。
UX(User Experience)
製品やサービスを使ったときに感じる体験全体のこと。
操作のしやすさ、見た目、感情的な印象も含む。
特にアプリやWebサイトの設計で重要視される。
例:スマホアプリが見やすく操作が簡単で使いやすかった。
CX(Customer Experience)
顧客が企業と関わるすべての体験のこと。
購入前から購入後までの印象や対応を含む。
良いCXは顧客のロイヤルティ向上につながる。
例:ネット注文から配送、アフターサービスまで一貫して快適だった。
カスタマージャーニーマップ
顧客の購入までの行動や感情を時系列で整理した図。
「認知→興味→比較→購入→使用→継続」などの流れを可視化する。
課題発見や施策設計に役立つマーケティングツール。
例:SNSで知り、Webで調べてから購入する流れをマップ化する。
4P
マーケティングの基本となる4つの視点。
Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販促)のこと。
企業がどのように商品を作り、届け、知らせるかを決める枠組み。
例:高品質なイヤホンを、適正価格でECサイトから販売し、SNSで宣伝する。
4C
顧客視点でのマーケティングの考え方。
Value(価値)、Cost(負担)、Convenience(利便性)、Communication(対話)で構成される。
4Pを消費者目線で言い換えたもので、顧客満足を高めるために使われる。
例:持ち運びやすいサイズで、価格も手ごろ、スマホで簡単に注文でき、問い合わせにも丁寧に対応する。
RFM分析
顧客を3つの軸で分析して分類する方法。
Recency(最近の購入)、Frequency(購入頻度)、Monetary(累計購入金額)。
優良顧客の発見やターゲティングに使われる。
例:最近頻繁に高額商品を購入した人に特別クーポンを送る。
アンゾフの成長マトリクス
製品と市場の新旧を組み合わせて成長戦略を考えるフレームワーク。
「市場浸透」「市場開拓」「製品開発」「多角化」の4象限に分類される。
リスクと成長性を比較して、戦略の方向性を検討できる。
例:既存製品を新しい地域に売り出す=市場開拓。
オピニオンリーダー
他の人に影響を与える力のある情報発信者。
流行や商品評価において他者の購買判断を左右する存在。
SNS時代ではインフルエンサーとほぼ同じ意味で使われることもある。
例:人気ブロガーが紹介した商品が一気に売れた。
オムニチャネル
複数の販売チャネルを連携させて一貫した顧客体験を提供する仕組み。
実店舗・ECサイト・アプリなどを統合し、シームレスな購買体験を実現する。
顧客の利便性を高め、購入のチャンスを逃さない。
例:店舗で試着した商品をスマホアプリから注文して自宅で受け取る。
ブランド戦略
自社の商品やサービスに特有の価値やイメージを持たせる戦略。
信頼や高品質、個性などを通じて他社との差別化を図る。
長期的な顧客との関係性づくりや価格競争からの脱却が目的。
例:高級感と信頼性をブランドに結び付け、高価格でも支持を得る。
プロダクトライフサイクル
製品が市場に出てから退場するまでの流れを4段階で表すモデル。
導入期・成長期・成熟期・衰退期に分けられる。
各段階で適したマーケティング施策が異なる。
例:新商品は広告に力を入れ、成熟期は利益重視に切り替える。
ポジショニング
競合の中で自社の商品やサービスがどう位置づけられているかを明確にすること。
差別化されたイメージを作り出し、消費者の記憶に残す。
戦略的な訴求ポイントの選定が重要。
例:安全性を重視する自動車ブランドとして印象付ける。
セグメントマーケティング
市場を性別・年齢・趣味などの特徴で細かく分け、それぞれに合った戦略をとる方法。
「誰に売るか」を明確にすることで、効率的な販売が可能になる。
マス向けではなく特定層向けの商品に適する。
例:シニア向けスマートフォンを使いやすく設計する。
ダイレクトマーケティング
顧客一人ひとりに直接アプローチする販売手法。
DM、電話、メール、SNSなどを通じて個別に情報を届ける。
効果測定がしやすく、すぐに反応を得やすい。
例:以前に購入した人に限定セールの案内メールを送る。
クロスメディアマーケティング
複数の異なるメディアを組み合わせて相乗効果を狙うマーケティング。
テレビCM、Web広告、SNS、雑誌などを連動させて訴求する。
認知度向上と記憶への定着が期待できる。
例:雑誌広告で紹介した商品に、QRコードでWeb限定動画へ誘導する。
インバウンドマーケティング
顧客から見つけてもらう形の集客手法。
ブログやSNS、動画、SEOなどで有益な情報を発信し、自然に関心を引く。
押しつけがましくない手法として評価される。
例:悩みを解決するコラムを読み、興味を持って製品ページへ訪れる。
ロケーションベースマーケティング
GPSなどの位置情報を使って、近くにいる顧客へ最適な情報を届ける手法。
店舗への誘導や地域限定のキャンペーンなどに活用される。
スマートフォンの普及により実施しやすくなった。
例:駅の近くにいる人にその場で使える割引クーポンを配信する。
プッシュ戦略
企業側から積極的に顧客に情報を届ける手法。
広告、営業、店頭販促などで購入を促す。
売り手主導のアプローチで短期的な効果を狙う。
例:店頭で声をかけて商品を手渡すキャンペーン。
プル戦略
顧客側の関心を引き、自然と買いたくなるよう仕向ける戦略。
ブランド力や口コミ、SNSでの共感などが鍵となる。
買い手主導のアプローチでファン化につながりやすい。
例:人気モデルがSNSで使っていることで話題になり、購入が増える。
インターネット広告
Web上に掲載される広告全般のこと。
検索エンジン、SNS、動画サイト、ニュースサイトなどに表示される。
ターゲットを細かく設定でき、費用対効果が高い。
例:検索履歴に基づいておすすめ商品が表示されるバナー広告。
オプトインメール広告
受信者の同意を得たうえで配信する広告メール。
迷惑メールと区別され、企業の信頼にもつながる。
開封率やクリック率を測定しやすい利点がある。
例:メルマガ登録者限定の割引情報を配信する。
バナー広告
Webページに表示される画像形式の広告。
ユーザーの目を引くために目立つデザインで作られることが多い。
クリックすると広告主のサイトや商品ページに移動する。
例:ショッピングサイトの右上に表示された「セール開催中」の画像広告。
リスティング広告
検索エンジンで検索したとき、検索結果の上や横に表示される広告。
キーワードに連動して表示されるため、購買意欲が高い人に届きやすい。
成果報酬型で、クリックされた回数に応じて費用が発生する。
例:「スマホケース 通販」で検索すると、広告付きのショップが上位に表示される。
SEO(Search Engine Optimization)
検索エンジンで上位に表示されるようにWebサイトを工夫する手法。
キーワードの選定やページの構成、表示速度の改善などが含まれる。
広告費をかけずに自然検索からのアクセスを増やせる。
例:「英会話 教室」で検索したときに、上位に来るように記事を最適化する。
A/Bテスト
2つのパターンを比較して、どちらがより効果的かを検証する方法。
広告文、Webデザイン、メールタイトルなどを変更して反応を比べる。
ユーザーの反応を数値で確認でき、改善に役立つ。
例:同じメールで件名だけ変え、どちらが多く開かれたかを比較する。
アフィリエイト
他人の商品やサービスを紹介し、成果が出ると報酬をもらえる仕組み。
個人のブログやサイトなどでも利用できる。
成果型広告の代表で「成果報酬型広告」とも呼ばれる。
例:ブログで紹介した本が購入されると報酬が発生する。
レコメンデーション
ユーザーの行動履歴や好みに基づいて商品や情報を提案する技術。
AIやアルゴリズムを使って、パーソナライズされた情報を提示する。
ネットショッピングや動画サイトなどで多く活用されている。
例:通販サイトで「この商品を見た人はこんな商品も見ています」と表示される。
デジタルサイネージ
ディスプレイなどの電子的な表示機器を使った広告手段。
駅、店舗、屋外などに設置され、動きのある映像で情報を発信する。
タイミングや場所に合わせて柔軟に内容を変更できる。
例:駅の改札上に設置された電子パネルで流れるイベント告知。
スキミングプライシング
新商品を高価格で発売し、初期段階で利益を多く得る戦略。
初期の高い需要を狙い、徐々に価格を下げて普及を図る。
革新的な商品やブランド力がある場合に効果的。
例:新型スマートフォンを最初は高価格で販売し、後から価格を下げる。
ペネトレーションプライシング
新商品を低価格で販売し、早期に市場に浸透させる戦略。
シェア拡大やブランド認知を狙うときに有効。
利益よりも市場の入り口づくりを重視する。
例:初回限定で格安プランを提供し、顧客を獲得する。
ダイナミックプライシング
需要や供給、曜日、天候などの状況に応じて価格を自動的に変動させる方法。
AIやデータ分析によってリアルタイムで価格を最適化する。
航空券、ホテル、ECサイトなどで使われる。
例:週末は宿泊料が高くなり、平日は安くなるホテルの料金設定。