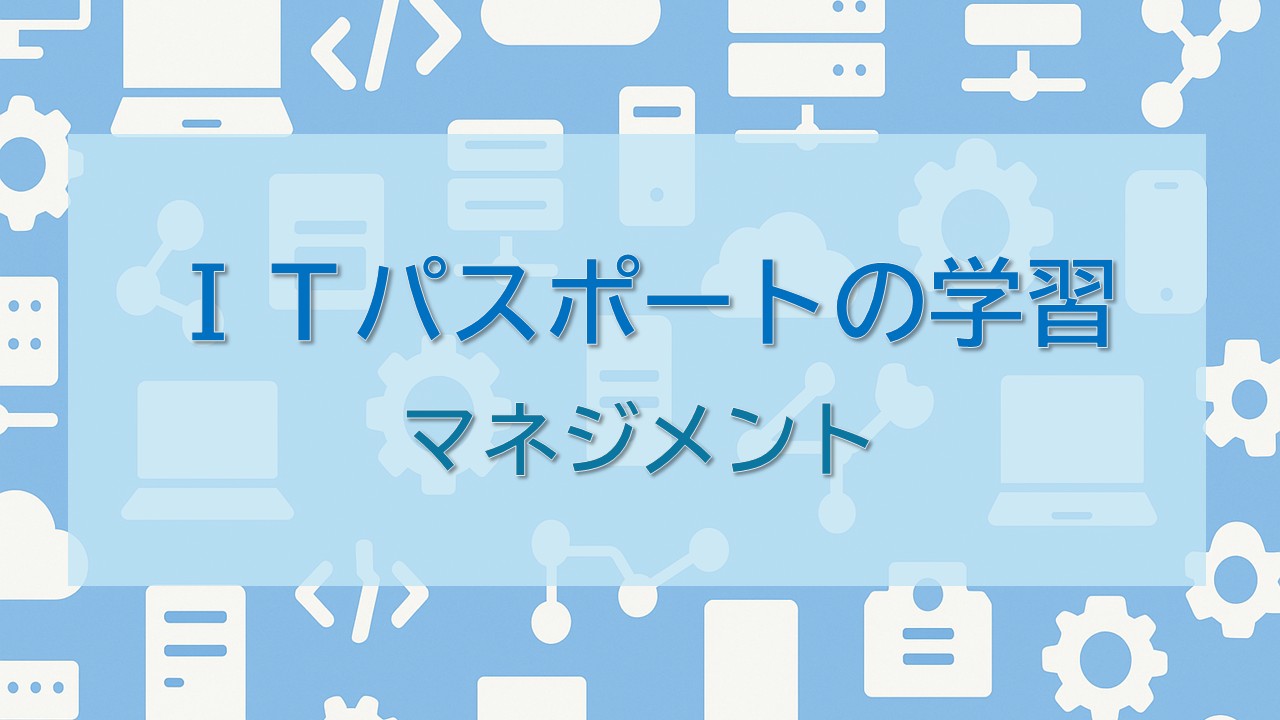サービスマネジメント
ITサービスを安定して提供し、継続的に改善していくための仕組みや活動。
利用者のニーズを満たすために、品質・コスト・提供時間などを管理する。
IT運用の現場で欠かせない考え方。
例:ネットワーク障害時の復旧対応から、今後の改善策までを一貫して管理する。
ITIL(Information Technology Infrastructure Library)
ITサービスマネジメントのベストプラクティス(成功事例)をまとめたガイドライン。
イギリス政府が発祥で、世界中の企業で標準的に使われている。
ITサービスの設計・提供・改善などを体系的に整理している。
例:ITILに基づいて、障害発生からサービス復旧までの手順を整備する。
サービスレベル合意書(SLA:Service Level Agreement)
サービス提供者と利用者の間で、提供するサービスの内容や水準を取り決めた文書。
可用性、応答時間、復旧時間などを数値で明示する。
責任の明確化やトラブル防止のために重要な契約文書。
例:月間稼働率99.9%をSLAで定め、達成できなかった場合は報告義務がある。
SLO(Service Level Objective)
SLAの中で定める、具体的な目標値。
システムやサービスの品質目標を数値で示す。
内部的な目標値として設定されることが多い。
例:応答時間は1秒以内、システムの稼働率は99.95%など。
SLI(Service Level Indicator)
サービスの品質を測定するための具体的な指標。
稼働率、遅延、エラー率など、サービス状態を定量的に表す。
SLOやSLAを評価するための基礎データとなる。
例:5分間に500件のエラーが発生した場合のSLIはエラー率10%。
サービスマネジメントシステム
サービス提供のための体制・ルール・手順を体系的に整えた管理の仕組み。
継続的な改善を目的とし、ISOなどの国際規格にも準拠できる。
サービスの質を一定以上に保つための土台となる。
例:インシデント対応や変更管理の流れを一元管理する仕組み。
サービスの要求事項
サービス利用者が提供側に対して期待・要求する条件や内容。
可用性、処理速度、対応時間などが含まれる。
要件として整理し、SLAや運用設計の基礎となる。
例:平日9時〜17時までに問い合わせに必ず回答してほしいという要求。
サービスレベル管理(SLM)
SLAに基づいて、サービスの品質が維持されているかを継続的に管理すること。
定期的なレビューや調整を行い、利用者満足度の維持を図る。
SLA違反を防ぎ、改善を促す重要な活動。
例:毎月の稼働率レポートをチェックして、目標を下回った場合は対策を講じる。
需要管理
ITサービスに対する利用者の需要(利用量)を予測し、リソースを適切に配分すること。
過剰や不足を防ぎ、効率的な運用を実現する。
システムの負荷や利用パターンの把握が重要。
例:繁忙期にはアクセスが集中するため、事前にサーバーを増強する。
サービス要求管理
利用者からの問い合わせ、要望、申請などの対応を管理する活動。
日常的なリクエストに対し、迅速かつ適切に対応する。
インシデントとは異なり、サービス中断を伴わない依頼が中心。
例:新しいアカウントの発行申請に対応する。
インシデント管理
サービスに支障を与える障害やトラブルに対し、迅速に復旧させるための活動。
影響を最小限にとどめることが目的。
根本原因の調査は含まれず、早期復旧が優先される。
例:ネットワーク障害が発生し、すぐに復旧作業を行う。
問題管理
インシデントの根本原因を分析し、再発防止のために対応する活動。
一時的な対応ではなく、長期的な解決を目指す。
インシデント管理と連携して実施される。
例:何度も発生するエラーの原因を突き止め、ソフトウェアを修正する。
構成管理
IT資産や構成要素(ハード・ソフト・ネットワークなど)を把握し、管理する活動。
構成情報を正確に保ち、変更の影響範囲を特定するために使われる。
構成管理データベース(CMDB)を用いることが多い。
例:サーバーの設置場所、OSバージョン、接続構成などを管理する。
変更管理
システムや構成に変更を加える際、リスクを抑えて適切に実施するための管理活動。
事前の評価・承認・実施・記録を一連の手順で行う。
サービスの安定性を保つために不可欠。
例:データベースのバージョンアップを変更管理手順に沿って行う。
リリース及び展開管理
変更されたソフトウェアや構成を、本番環境へ安全に展開するプロセス。
検証、スケジューリング、通知などを含む。
リスクの少ない方法で段階的にリリースすることが重視される。
例:新機能を深夜に段階的にリリースして影響を最小限に抑える。
サービス可用性管理
サービスが安定して利用可能な状態を保つための管理。
稼働時間、故障率、復旧時間などを監視・分析する。
利用者にとって重要な品質指標のひとつ。
例:稼働率99.9%を維持するために、定期的な点検を行う。
サービス継続管理
災害や重大な障害が発生しても、サービスを継続・再開できるように備える活動。
BCP(事業継続計画)との連携が重要となる。
緊急時対応手順や代替手段を準備する。
例:地震でデータセンターが使えなくなった場合の代替サイトを用意する。
サービスの報告
サービスの運用状況、インシデント対応、SLA達成状況などを報告する活動。
定期的な報告で、利用者や関係者と現状を共有する。
透明性のある運用に役立つ。
例:月次で稼働率や問い合わせ件数を報告する。
継続的改善
サービスの質を維持・向上させるため、日々の運用を見直し改善を続けること。
小さな改善を積み重ねることで、大きな成果につながる。
PDCAサイクルとともに運用されることが多い。
例:問い合わせ対応時間を短縮するため、手順書を見直す。
PDCA
Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)のサイクル。
継続的な改善を行うための基本的な手法。
品質管理や業務改善に広く活用されている。
例:マニュアル改善の計画を立て、実施し、効果を評価して再調整する。
サービスカタログ
提供しているサービスの内容、条件、手順などをまとめた一覧。
利用者にとってのサービスの見える化を目的とする。
ITサービスの窓口としての役割もある。
例:PC貸出、アカウント発行、障害対応などの手順を記載する。
エスカレーション
自分の対応範囲を超えた問題や判断を、上位の担当者や部署に引き継ぐこと。
問題を迅速に解決するための仕組み。
マニュアルやルールに従って段階的に行う。
例:障害の対応が難しい場合に、専門部署へ連絡する。
サービスの移行
古いシステムから新しいサービスへ切り替える作業。
データ移行、操作説明、リリースなどを含む。
トラブルを避けるため、計画的に段階を追って進める。
例:旧メールシステムからクラウドメールサービスへ移行する。
サービス受入れ基準
サービスを本番環境で正式に運用するために必要な条件。
テスト結果やドキュメントの整備、関係者の合意などが含まれる。
基準を満たしていることを確認してから運用を開始する。
例:すべての試験に合格し、操作マニュアルが用意されている状態。
サービスデスク
利用者からの問い合わせや障害連絡を受け付ける窓口。
トラブル対応、情報提供、エスカレーションの管理などを行う。
IT部門と利用者をつなぐ重要な役割を担う。
例:パスワードを忘れた際のリセット依頼を受け付ける。
サービス要求管理
日常的な申請や問い合わせに対応し、記録・処理する業務。
再発防止や業務改善のための分析にも使われる。
インシデントとは異なり、障害でない要求を扱う。
例:新しいアカウントの発行依頼を処理する。
SPOC(Single Point Of Contact)
単一の問い合わせ窓口の略。
利用者がどのような内容でも、最初に連絡する窓口を一本化する仕組み。
混乱や対応漏れを防ぎ、効率的な対応を実現する。
例:社内のすべてのIT関連問い合わせはサービスデスク1か所で受ける。
FAQ
よくある質問とその回答をまとめた資料やWebページ。
問い合わせ件数の削減や自己解決の支援に使われる。
サービスデスクの負荷軽減にも貢献する。
例:「ログインできないときはどうするか」といった質問と回答を掲載する。
チャットボット
自動で応答するプログラムにより、問い合わせに対応する仕組み。
定型的な質問に素早く対応でき、24時間稼働が可能。
AIを活用して徐々に学習し、回答精度を高めることもできる。
例:Webサイトで「パスワードを忘れた」と入力すると対応方法を案内する。
AIOps
AI(人工知能)を活用して、IT運用業務を自動化・高度化する手法。
異常検知、原因分析、予測などを人間の代わりに行う。
運用負荷の軽減や迅速な対応が可能になる。
例:サーバーの異常をAIが検知し、通知と一次対応を自動で実施する。
ファシリティマネジメント
建物や設備、電力、空調、ネットワークなどのITインフラを効率的に管理する活動。
快適で安定したITサービス環境を維持することが目的。
運用コストの最適化や省エネ対策、安全性の向上にも貢献する。
例:データセンターの温度や湿度を監視して設備を管理する。
グリーンIT(Green of IT)
IT機器の省電力化や資源の効率的な利用によって環境負荷を減らす取り組み。
電力使用量の削減、廃棄物の削減、再利用の促進などが含まれる。
地球温暖化対策や企業の環境配慮姿勢としても注目される。
例:サーバーを仮想化して台数を減らし、消費電力を削減する。
無停電電源装置(UPS:Uninterruptible Power Supply)
停電時にも一時的に電力を供給し、システムを安全に停止または継続させる装置。
バッテリー内蔵で、瞬断や停電からサーバーや機器を保護する。
情報システムの可用性を確保するために欠かせない。
例:突然の停電時でも、UPSによりサーバーを安全にシャットダウンできた。
自家発電装置
商用電源が使えなくなったときに、自社で電力を供給するための発電装置。
大規模な障害や災害時にもITサービスを維持するために使われる。
UPSと組み合わせて利用されることが多い。
例:台風で停電しても、自家発電によりシステムを運用し続けた。
サージ防護
雷や突発的な電圧上昇(サージ)から機器を守るための対策。
サージ吸収素子などの装置を用いて、機器の損傷を防ぐ。
電源や通信回線に設置されることが多い。
例:雷の多い地域では、ネットワーク機器にサージ防護を施す。